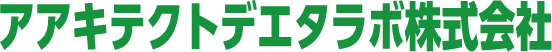ろ過装置の故障、見落としていませんか?寿命とメンテナンスサインを徹底解説
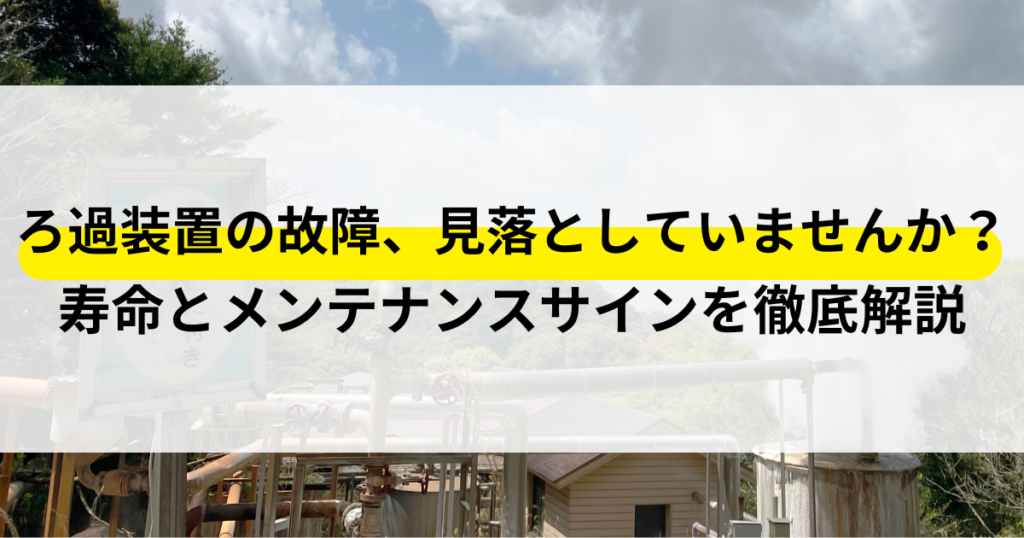
ろ過装置は温泉施設の水質維持には欠かせない設備です。「まだ大丈夫」と思っていると、思いがけないトラブルを引き起こしてしまうかもしれません。
この記事では、ろ過装置の寿命やメンテナンスのタイミング、見落としやすい異常のサインについて解説します。
ろ過装置の一般的な寿命とは

温泉施設において、ろ過装置は水質を維持するための重要な設備です。しかし、どんな設備にも寿命があります。
ろ過装置の不具合は目に見えにくいため、気づかないうちに進行していることも少なくありません。
ろ過装置とろ材の一般的な寿命
ろ過装置本体の耐用年数は一般的に10〜15年程度です。一方、実際のろ過を担うろ材(砂・セラミックなど)は、3〜5年が交換の目安となります。ただし、使用頻度や水質によって寿命は前後するため、一概には言えません。
特にかけ流し温泉の場合、含有成分によってろ材の劣化スピードが大きく変わることがあります。ろ材の状態を定期的にチェックし、最適なタイミングでのメンテナンスを心がけることが重要です。
定期的なメンテナンスの必要性
ろ過装置は「見えない部分」で働いているため、故障や性能低下に気づきにくいと言われます。メンテナンスの先送りは思わぬトラブルを招くかもしれません。定期的なメンテナンスにより、装置の長寿命化と安定した水質の維持ができるでしょう。
急な故障による営業停止は、お客様の信頼低下につながるリスクもあります。予防保全の考え方で定期的なメンテナンスを行うことが大切です。
見落としやすいろ過装置の異常
「まだ動いているから大丈夫」と思っていても、実は性能が大きく低下している場合もあります。日常点検だけでは見落としがちな問題も少なくありません。
ただ、ろ過装置の異常は専門的な知識がなくても気づけるサインがあります。
ろ過装置またはろ材の4つの劣化サイン

ろ過装置やろ材の劣化は、いくつかのサインで気づくことができます。早期発見が大きなトラブルを防ぐカギです。
ここではろ過装置またはろ材の劣化サインについて解説します。
サイン①:水の透明度が落ちる
温泉の浴槽内の水の濁りが取れにくくなっている場合、ろ材の性能劣化の低下が考えられます。以前は澄んでいた湯が、徐々に透明度を失っていく場合は要注意です。
お湯の透明度は、お客様が最も気にする水質の指標の一つです。濁りのある湯は、見た目の印象だけでなく、衛生面での不安も与えてしまいます。
サイン②:塩素濃度が安定しない
消毒用の塩素濃度が安定しない日が増えた場合、ろ材や配管にバイオフィルム(菌の膜)が発生している可能性があります。バイオフィルムが形成されると、消毒剤が効きにくくなり、水質管理が難しくなります。
塩素濃度の測定値が急に下がったり、いつもより多くの消毒剤を使わないと基準値を維持できなくなったりした場合は、ろ過装置の劣化を疑いましょう。
サイン③:ろ過ポンプの運転音がうるさい
ろ過ポンプの運転音が通常より大きくなった場合、ろ材やフィルターの目詰まりにより、ポンプにいつも以上の負荷がかかっているサインです。このままでは、モーターの故障や寿命短縮につながる恐れがあります。
普段と違う音や振動に気づいたら、すぐに点検することをおすすめします。
サイン④:レジオネラ菌の検出リスクが上昇
レジオネラ菌が検出されやすくなるのは、ろ材の劣化や汚れによるろ過不全が原因となっていることがほとんどです。きちんと機能しているろ過装置は、水中の微生物や有機物を除去し、レジオネラ菌の増殖を抑える効果があります。
万が一、レジオネラ菌が検出された場合、行政指導や営業停止処分となるケースもあります。
ろ過装置の部品別寿命は?

ろ過装置はさまざまな部品から構成されており、それぞれに寿命があります。
正しいタイミングでの交換やメンテナンスを行うためには、各部品の寿命目安を知っておくことが重要です。
一般的な寿命の目安
ろ材(砂・活性炭など)の寿命は約2~5年、フィルターカートリッジは約半年~1年、配管やバルブ類は約10年程度、ろ過装置本体は約10~15年が一般的な寿命となります。
| 部品名 | 交換・点検の目安 | 備考 |
| ろ材(砂・活性炭など) | 約2~5年 | 目詰まりや劣化が進む前に交換推奨 |
| フィルターカートリッジ | 約半年~1年 | 小規模施設で使用される場合が多い |
| 配管やバルブ類 | 約10年程度 | 腐食やスケールによるトラブルも多い |
| ろ過装置本体 | 約10~15年 |
ただし、これらはあくまで目安であり、使用頻度や水質(鉄分・マンガン・濁度)によって前後します。
老朽化したろ過装置のリスク
老朽化したろ過装置や、清掃不十分なろ材は、汚れやスライムが堆積し、細菌が繁殖しやすくなります。また、通水が不十分になることで殺菌処理が行き届かなくなり、レジオネラ菌の繁殖源になることがあります。
実際に温浴施設でレジオネラ症の集団感染が発生した例もあります。お客様の安全と施設の信頼を守るためにも、定期的なチェックと部品交換は欠かせません。
ろ過機の異常はなぜ見落とされがち?

ろ過装置の異常や劣化は、なぜ見落とされがちなのでしょうか。
その理由を理解することで、効果的な点検方法や管理体制を構築することができます。
見た目では劣化がわかりにくい
ろ材は浴槽水の中にあるため、変色や崩れ以外の変化が分かりづらいでしょう。目視で確認できる部分は限られており、実際のろ過性能は外観だけでは判断できません。
定期的な性能チェックや専門業者による診断が重要です。
日常点検で異常が出にくい
毎日の運転が可能でも、性能の低下がじわじわ進行しているケースが多いでしょう。一見すると問題なく動いているように見えても、実は効率が大きく落ちている可能性があります。
温泉の水質は日によって変動するため、ろ過装置の性能低下を水質の自然な変化と混同してしまうことも少なくないでしょう。
「まだ動くから大丈夫」という油断
実際には、ろ過装置の性能が低下していても衛生基準を下回っている可能性があります。「故障していなければ問題ない」という考え方では、気づかないうちに水質が悪化しているかもしれません。
予防保全の観点から、定期的なメンテナンスと部品交換を計画的に行うことが重要です。
メンテナンスと交換の判断基準

ろ過装置を正しく管理するためには、メンテナンスのタイミングと交換時期の判断が重要です。
定期的な点検のポイント
ろ過装置の日常点検では、水質の変化に注目しましょう。濁りや臭いの変化があれば記録しておくことが大切です。
また、ポンプの音や振動、圧力計の数値も定期的にチェックするとよいでしょう。
日々の小さな変化を見逃さないことが、大きなトラブル防止につながります。
専門業者による検査の重要性
ろ過装置の専門的な診断には、業者による流速チェックやろ過効率の測定が効果的です。これらの専門的な検査によって、目視では分からない内部の劣化状況を把握できます。
業者による定期的な専門検査は、突発的な故障リスクを低減し、計画的な設備更新を可能にします。
交換時期を判断する具体的な基準
ろ材は定期的に洗浄していても徐々に寿命が来ます。3年以上経過したろ材は目に見えなくても劣化リスクが高まるため、定期交換と衛生チェックをセットで行いましょう。
「まだ使える」という判断よりも、「安全性を優先」する姿勢が大切です。
「ココチー」で設備状態を遠隔監視

温泉施設の設備管理をより効率的に行うなら、IoT技術を活用した監視システム「ココチー」の導入も検討してみてください。当社が開発・販売している「ココチー」は温泉の湯温・湯量だけでなく、設備状態などもリアルタイムで遠隔監視できるシステムです。
ろ過装置の異常をいち早く検知し、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。スマホやPCで温泉設備をリアルタイム監視でき、異常を検知すると即座に通知が届くため、迅速な対応ができるでしょう。
温泉の水質管理でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
温泉経営のお悩み、そのままにしていませんか?
「温泉経営がなかなかうまくいかない…」そんなお悩みを、アアキテクトデエタラボの問題解決調査サービスやシステム導入で解決しませんか?
当社では担当者が実際に施設へ出向き、しっかりと現状を確認し、具体的な改善策をご提案します。
日本全国多数の事例を基にお客様に喜ばれる施設作りをサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。